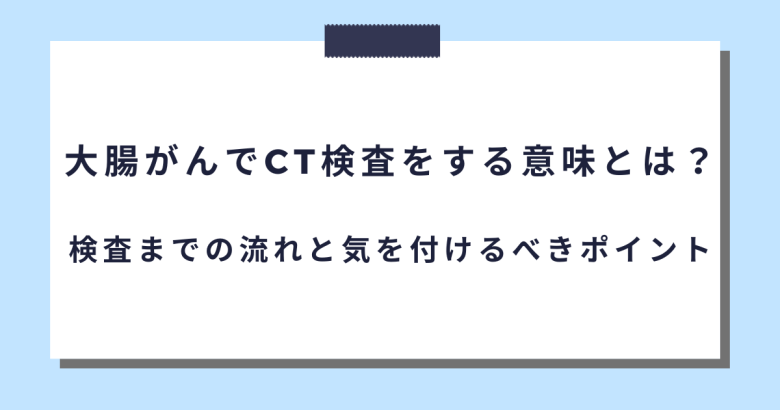
CTの検査って安全なの?
大腸がんの検査でCTを撮るのはなんのため?
大病しない限り、CTの検査を受けた経験がある人はあまりいないでしょう。
CT検査をはじめて受ける人に向けて解説しました。
この記事を読めば不安なことや疑問が解消できるので、安心してCT検査を受けられますよ!

CT検査の概要・目的
はじめに、CT検査とは何なのか述べていきます。
CT検査とは?
・360°からX線を当てて得たデータを、パソコン上で処理して体の断面像の画像を得る検査
・ベッドに横たわり、ドーナツの中に入って移動しながら撮影をする
・検査時間は10-20分、10秒程度の息止めを複数回行う
CT検査では体の輪切り画像を得ることができます。
レントゲン写真に比べて血管の石灰化や肺炎の有無がわかりやすいのが強みです。
MRI検査と似ていますが、決定的に違うのは撮影時間の早さ。
全身をくまなく撮影するときにCT検査はとても便利です!
大腸がんのCT検査では次のようなことを見ています。
CT検査で見ているところ
- おなかの状態の確認(手術歴や大腸の状態など)
- 大腸がんの広がり
- 大腸の周辺や全身のリンパ節が腫れていないか
- 遠隔転移しやすい臓器(肝臓、肺など)に病変がないか
このようにCTは病気の診断にとても役立つ検査ですが、次のような人は受けられないので注意が必要です。
CT検査を受けられない人
- 妊婦
→CT検査の被ばくが、おなかの胎児に悪影響になる - ペースメーカーやICDが体内に入っている人
→一定のX線が当たると、誤作動のリスクあり。部位によっては撮影可能。 - 体内にバリウムが残っている人
→バリウムによって大腸の病変が見えなくなる。バリウムがなくなってからの検査が好ましい
上記の内容に当てはまる場合は検査前に医師や看護師に伝えておくと安心です
ヨード造影剤とは何か
大腸がんの場合は、がん病変を見やすくするためにヨード造影剤というお薬を使うことが多いです。
そこでヨード造影剤について解説していきます。
ヨード造影剤とは?
- 造影剤とは、体内に投与して画像上で病変の有無や体内の状態をわかりやすくするためのお薬のこと
- CT検査(ヨード造影剤)、MRI検査(ガドリニウム系造影剤)、超音波(ガス気泡)、バリウム(胃検診)があるが、各検査で造影剤の種類は異なる
- CTのヨード造影剤はほかの造影剤に比べて副作用のリスクが高い
- 体質や健康状態によって検査を受けられない人や、前もって準備が必要な場合がある
ヨード造影剤でがん病変がわかりやすくなる仕組み
CT検査でヨード造影剤を使うと、体内の状態やがんの病変が見えやすくなります。
がんは大きくなるためにたくさんの血流を必要とするからです。
血管に直接投与した造影剤は、血流に乗って全身をくまなく巡り、がんに取り込まれる血流にも、造影剤が入り込んでいく……
造影剤が血流の情報を反映するため、がんが見えやすくなります
がんが画像上で白く見えていれば、それは造影剤がよく取り込まれている証拠。
血流が豊富にあるがんであることを意味します。
このようにして、ヨード造影剤を投与した撮影ではがん病変が見つけやすくなるのです。
ヨード造影剤の副作用
造影剤のデメリットは一定の確率で副作用が発生するところです。
ヨード造影剤の副作用は、くしゃみのような軽い症状からアナフィラキシーショックほどの重症なものまでさまざま。
副作用は人によって現われる症状が大きく異なりますが、次に示すような症状が見られることが多いです。
主なヨード造影剤の副作用
- 軽い副作用
くしゃみ、熱感、息苦しさ、吐き気、嘔吐、かゆみ、じんましん
- 重い副作用
呼吸困難、アナフィラキシー、意識障害、血圧低下
一般に副作用の現われる確率は全体の3%と言われていますが、熱感(暖かい感覚)はほぼ100%の人に見られます。
また重い副作用は全体の0.004~0.04%(2500人~25000人に1人)に見られる症状で、非常にまれです。
撮影後の数分間の経過観察中に症状が良くなることがほとんどです
ただ体調不良や寝不足のような健康状態の不調があると、副作用が出やすいので体調を整えておきましょう!
ヨード造影剤を使う際に注意が必要な人の特徴
特定の疾患があると、ヨード造影剤を使えなかったり副作用のリスクが高まる場合があります。
ヨード造影剤の使用に注意が必要な人
腎臓の機能が低下している人
腎臓の機能が低下していると、程度によっては造影剤を使えない場合があります。
なぜなら造影剤により腎臓のはたらきが悪化するリスクがあるから。
造影剤は腎臓を通過して尿として排泄されるため、腎臓のはたらきが悪いといつまでも腎臓に留まってしまいます。
大半の場合この腎臓の機能の低下は一時的ですが、まれに機能が元に戻らず血液の人工透析が必要になることもあります……。
腎臓のはたらきが悪いと、使える抗がん剤が制限されることもあって治療に支障が出るので、腎臓に負荷をかけないことはとても大切です
造影剤を使えなくなる目安は、eGFR(腎臓機能の数値)が30以下の場合。
eGFRの値が30~40程度の場合は、腎臓を守るために点滴することもあります。
脱水したままだと、体内に造影剤が残るため腎臓の負荷になります。しっかりと水分補給をしましょう!
糖尿病のお薬を飲んでいる人
糖尿病のお薬を飲んでいる人も造影剤の検査には注意が必要です。
糖尿病薬が造影剤と反応して、乳酸アシドーシスという体に害をもたらす状態を引き起こすからです。
乳酸アシドーシスとは?
- 乳酸が血液中に溜まることによって血液が酸性化している状態のこと
- 酸性化を放っておくと、感染症にかかりやすくなったり、最悪の場合死に至ることもある
- 造影剤と反応して乳酸アシドーシスを引き起こすのは、一部の糖尿病薬だけ
造影剤と反応する糖尿病薬は「ビグアナイド」系という種類であり、腎臓のはたらきが悪い場合に問題になります。
必要に応じて次のような糖尿病薬の休薬が求められます。
糖尿病薬の休薬と腎臓の機能について
- eGFR<30 造影剤検査不可
- 30<eGFR<45 糖尿病薬は検査前後の48時間投与禁止
- 45<eGFR<60 糖尿病薬は検査後の48時間投与禁止
- 60<eGFR 糖尿病薬の検査前後の投与なし
eGFRは腎臓のろ過する能力を示す数値。採血によってeGFRの測定をします
ビグアナイド系の糖尿病薬を飲んでいる人は、腎臓機能の数値を意識しておきましょう。
造影剤副作用を引き起こしやすい疾患
ヨード過敏症や重篤な甲状腺疾患、気管支ぜんそくの基礎疾患がある人は造影剤の副作用が起きる確率が高まります。
中でも気管支ぜんそくの場合は、健常の人と比較して副作用の確率が3倍以上になることがわかっています。
造影剤を使用するときには、現状の基礎疾患についても医師や看護師に話しておくと安心です!
CT検査の流れと気をつけたほうが良いポイント
CT検査の流れと検査時に気をつけたほうが良いポイントを解説します。
CT検査は次のような流れで行います。
問診
静脈ルート確保*
検査室入室&衣服の金属類、貴重品類のチェック
造影剤使用歴と副作用歴の有無を確認*
撮影①
造影剤を注射から投与*
撮影②
経過観察&静脈ルート抜去*
*の印は造影剤を使う場合に行う内容です。
CT検査自体に副作用はないので、造影剤を使わない場合の経過観察は必要ありません。
step
1問診
検査前に問診をとります。主に次の内容について確認します。
問診で確認することリスト
- 造影剤歴・お薬の副作用歴
- 副作用になりやすい基礎疾患の有無
- 糖尿病の有無(有りの場合は、飲んでいる糖尿病薬の名前を記入)
- 腎不全の有無
- 体重(造影剤量が体重で決まるため)
- 妊娠の有無
step
2静脈ルート確保
検査室に移動する前に静脈注射で造影剤を投与するための針を入れます。
基本は22Gという一般的な健康診断で使うものとほぼ同じ太さの針を使います。
ただ体重が重い場合や、術前で血管の情報が欲しい場合は、造影剤をたくさん投与する目的で、一回り大きい20G太い針を入れることもあります。
静脈に残した針は、金属の針ではなくプラスチックの注射針なので多少の腕の曲げ伸ばしをしても大丈夫です。

飲水制限がない場合は、検査の待ち時間に水分補給することも大切です。
水分摂取で腎臓への負荷を抑えることができます。
step
3検査室入室&衣服の金属類、貴重品類のチェック
検査室に入室したあとは、金属類のチェックを行います。
金属類が身に着いた状態で撮影すると、画像中に見えない部分ができてしまうためです。
次のようなもののうち、あらかじめ取り外せるものは検査前に外しておくと良いですよ!
検査時に外す必要があるモノ
- ピアス、ネックレス、指輪などのアクセサリー
- ベルト・ズボンのファスナー(ズボンは撮影範囲外まで下げればOK)
- ブラジャーの金属、キャミソールの長さを調節するための金具
- ヘアピン、入れ歯
- カイロ、湿布
step
4検査説明と造影剤使用歴・副作用歴の有無を確認
検査直前に検査時の注意事項の説明と、造影剤の使用歴・副作用歴の再確認を行います。
また次のような検査説明があるので軽く覚えておくと安心です。
CT検査の注意事項
- アナウンスに合わせて息止めをする(10秒ほど)
- 息が止まっていないと画像がブレてしまうので、再度撮影することがある
- 検査中は指示がない限り体を動かさない(複数回撮影して3Dの画像を作る場合がある)
- 造影剤投与中に針の先に痛みがないか(造影剤が血管から漏れることがある)
- 造影剤投与中に気分が悪くなったら伝える(副作用の場合は造影剤の投与を止める必要があるため)

step
5撮影①
撮影の際には、はじめに息止めで正面と側面のレントゲンを撮ります。
目的は2つ。
CTの輪切り画像を撮影する範囲を決めるため、もう1つは過剰な被ばくを抑えるためです。
レントゲン写真の情報から、機械が割り出した最適な撮影条件で撮影することができます。

step
6造影剤を注射から投与
2枚のレントゲンを撮ったのち、造影剤を使います。
注射の針が入った静脈に、専用の投与機を使って一定の速度で造影剤を投与します。
普通の撮影であれば1分かけて投与しますが、外科手術の前やCTコロノグラフィを行う場合は動脈や静脈の情報を得るために20-30秒ほどの短時間で一気に造影剤を投与します。
造影剤を使うと体が暖かくなりますが、造影剤を早く入れるほどその変化は急激になります。

step
7撮影②
造影剤が投与された後は撮影を行います。
1分間で投与した場合は30秒後、20-30秒で投与した場合は数秒後から息止めで撮影をします。
撮影内容によっては、造影剤を使用してから時間を空けて複数回撮影することもあります。
息止めができていなかったり、くしゃみが出て画像がブレた場合には、再度撮影し直すこともあります。

step
8経過観察&静脈ルート抜去
造影剤の検査を行ったあとは、時間を空けて経過観察をします。
造影剤による副作用の大半は検査終了後から5分間に現われると言われています。
そのため、検査後は検査室周辺で体調に変わりがないか観察をします。
待機時間中に問題がなければ静脈の針を抜いて他の検査や帰宅して大丈夫です。
また飲水に制限がない限り、早く体外に造影剤を排出するために普段より多めに水分補給をしましょう。

CT検査に関するQ&A
CT検査に関してのよくある質問のQ&Aを解説します。
気になるものがあれば確認してみてくださいね。
CT検査のよくあるQ&A
CT検査の費用はいくら?
CT検査の費用の総額と3割負担だった場合の値段で次にまとめました。
| 検査内容 | 検査費用 | 3割負担額 |
| CT 単純(造影剤なし) | 20000-30000円 | 6000-9000円 |
| CT 造影(造影剤あり) | 30000-43000円 | 9000-13000円 |
造影剤は種類によって大きく金額が異なります。

月に何回もCTの撮影をしても大丈夫?
結論から言うと、月数回程度であれば全く問題ありません。
放射線による被ばくの量は法令で定められていますが、医療によって受ける被ばくする量の制限がありません。
ただしこれは、患者にとって必要だと医師が判断した場合に限ります。
医師は被ばくのデメリットと、検査を受けることによるメリットを天秤にかけて検査をオーダーしています。
だから不当にたくさんの放射線を浴びることはありません。
できるだけ被ばくが増えないように、医師や放射線技師が撮影条件の検討も重ねているので安心です
検査の前は絶食は必要?
基本的に絶食は不要です。
ただCTコロノグラフィにより小さながん病変を見る場合には、便があると見えにくくなるので検査前日の検査食があったり、消化の良いモノを食べるように指示があります。
食事に関して指示がない場合は確認してみると良いですよ!
CT検査は怖い検査じゃない!
CT検査は、被ばくや造影剤の使用による副作用、腎臓への負荷など気がかりな部分も多いでしょう。
ですが数回のCT検査では心配するほどの被ばくではないですし、副作用は出ること自体がまれです。
仮に症状が出たとしても大半はすぐに良くなります。
腎臓への負荷も検査前に水分補給や点滴をすることで大きく減らすことができます。
準備しておけばCTはまったく怖くありません。検査を受けるときにはまた確認してみてくださいね!
-
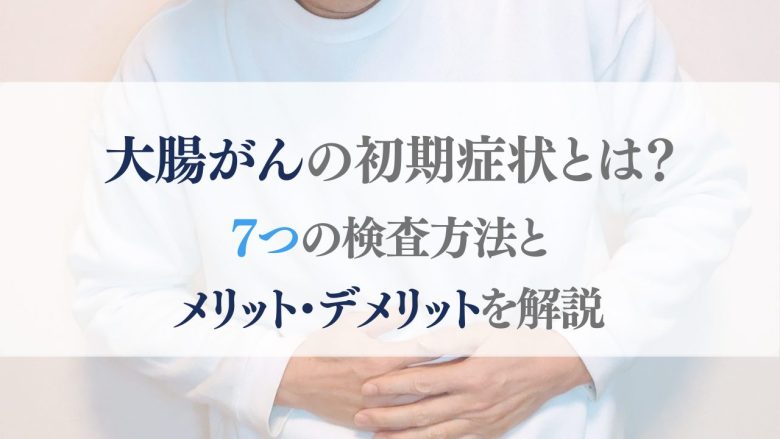
-
大腸がんの初期症状とは?7つの検査方法とともに解説

